
不動産の評価のし方
前回の相続税の計算方法で分かるとおり、不動産の評価額(相続税の計算上の価値)が分かれば、何とか相続税額までたどり着くことができる。そこで今回は、不動産の評価方法をお伝えする。
(1)宅地の評価のし方
大きく次の二つの方法がある。これはどちらで計算してもいいということではなく、下記(イ)の路線価がある土地については路線価で計算しなければならない。インターネットの検索で、「路線価図」と入力すると路線価図のページが出てくるので、該当地域を選んで路線価を確認してみてほしい。
(イ)路線価方式
路線価(㎡単価)×面積(㎡)
路線価とは、宅地の接する道路に、国税庁が1㎡あたりの単価を決めているものである。
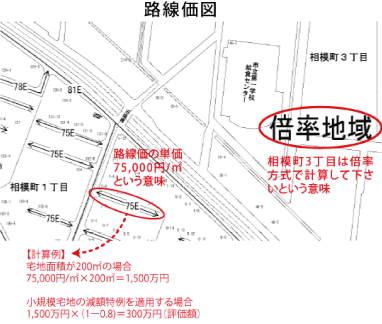
実は、土地はきれいな正方形や長方形だけとは限らないし、高低差があったり、高架線や線路の側など、同じ面積でも条件はさまざまなので、さらにそれらの条件に合わせて加減算をして最終的な評価額となる。ただし今回は、なるべく簡単に概算の相続税額を求めるのが目的なので、ここまでとしておく。
(ロ) 倍率方式
宅地の固定資産税評価額×地域毎に決められた一定の率固定資産税
評価額は、毎年4月くらい に市区町村から送られて くる固定資産税通知書に 記載されている。ただし、 固定資産税課税標準額 とは違うので注意。
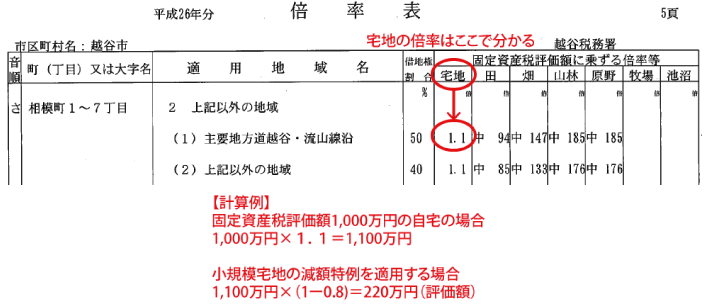
(2)アパート・マンションの貸家がある宅地の評価方法
(1)の方法によって計算した評価額×80%として、概算で求められる。正確には(1)×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)であるが、ここでも相続税の概算を求めるという主目的から省略することとする。 また、場合によっては小規模宅地の減額特例が使えるが、これも同様に省略する。
(3) 家屋の評価のし方
(イ) 自分で居住するための家屋固定資産税評価額×1.0
(ロ) 貸家固定資産税評価額×1.0×0.7
正確には(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)である。
不動産の評価は、厳密に計算しようとすれば相当な知識と労力が要求される。今回は、あくまでも一般の人が概算でどのくらいになるかを調べるための基本を紹介している。したがってより精緻な税額を求めるのであれば、税理士等の専門家に依頼するのがベターだ。
【タグ】#税金コラム,#ポラス,#不動産売却,#相続,











