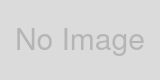住宅の売却を検討している方は、それぞれの違いについて理解しておきましょう。
譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得た利益のことです。
この利益は課税対象であるため、確定申告を行い、住民税と所得税を納税しなくてはいけません。
譲渡所得の課税方法
譲渡所得の課税方法は、所得期間によって定められた税率を譲渡所得に適用するという方法になっています。譲渡所得の計算
譲渡所得に関しては、以下の方法で求めることが可能です。
譲渡所得=不動産を売却した得た金額-(取得費+販売活動にかかった金額)
税額の計算
税額の計算方法ですが、至ってシンプルで、固定の税率を譲渡所得税にかけるだけです。この税率ですが、先ほども説明したとおり住宅の所有期間など住宅の条件によって適用される割合が異なってくるため、具体的な割合については後述します。
短期譲渡所得とは
住宅の所有期間によって、譲渡所得に課税する割合は異なります。ここでは短期譲渡所得について解説をしていきます。
短期譲渡所得とは
短期譲渡所得とは、売却した年の1月1日現在で「所有期間が5年以下」の場合に課税される所得のことです。非常に短い期間しか所有していない住宅に関しては、最も税率が高くなるのです。
短期譲渡所得でかかる税金
短期譲渡所得でかかる税金は、所得税の場合だと30.63%、住民税の場合だと9%となり合計で39.63%が税率となります。また、これとは別に復興特別所得税がかかります。その税率は基準所得税額×2.1%となっており、計算方法は全く同じです。
税金の計算方法
先ほども説明したとおり、税金の計算方法は譲渡所得に税率をかけるだけとなっています。
所得税=譲渡所得×30.63%
住民税=譲渡所得×9%
長期譲渡所得とは
続いては、長期譲渡所得について解説をしていきます。
長期譲渡所得とは
長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日現在で「所有期間が5年超」の場合に課税される所得のことです。所得期間が長くなると、税率も少なくなります。これは、築年数が長くなることによって、そもそも売却価格が安くなることに起因しています。
また後述しますが、さらに長い期間所有して、10年を超えると特例控除を受けられる場合があります。それが適用されると、さらに税率は下がります。
長期譲渡所得でかかる税金
長期譲渡所得でかかる税金は、所得税の場合だと15.315%、住民税の場合だと5%となっており、合計で20.315%が税率となります。また、短期譲渡所得と同じように復興別所得税もかかります。税率に関しては、短期譲渡所得税の場合と同様です。
税金の計算方法
税金の計算方法は、短期譲渡所得税と同じです。
所得税=譲渡所得×15.315%
住民税=譲渡所得×5%
短期譲渡と長期譲渡はどちらがお得?

短期譲渡と長期譲渡は税率が異なるのですが、それ以外にも支払わなくてはいけないお金が異なります。総合的に考えて、どちらの方がお得なのでしょうか。
建物の築年数は短いと価格が上がる
建物の築年数は短ければ短いほど価格が上がります。つまり、早くに売却をすれば税金として納めなくてはいけない額は多くなるのですが、そもそも売却価格が高いので結果的に手元に残るお金は多いと考えることもできるのです。しかし、住宅の構造によっては、築年数が経過していても値段が落ちづらい住宅もあります。そのような住宅の場合は、税率が下がるまで所有した後で売却をした方が、手元に残るお金は多くなりやすいでしょう。
固定資産税は短期間だと負担が軽い
毎年、支払わなくてはいけない税金に固定資産税があります。固定資産税は短期間だと非常に負担が軽いのですが、長期間になると負担する額が多くなっていきます。固定資産税に関していえば、早急に売却をした方が圧倒的にお得であるといえるでしょう。しかし、最終的に手元に残るお金で考えるとなると、どちらがお得かどうかは住宅によって異なるため、一概に判断することはできません。
どうしても知りたいという方は、不動産会社に査定だけをお願いしてみるのをおすすめします。
不動産売買の損失が出る場合
不動産売買において、損失が出る場合があります。その場合について確認をしていきましょう。
不動産売買の損失が出る場合
不動産売買において損失が出る場合というのは、不動産を購入した金額よりも不動産を売却した金額の方が低かったときに起こります。この場合は、結果的に手元に残るお金がマイナスとなっているので、確かに税金を納める必要はないのですが、一切の利益となっていません。
不動産売買において損失が生まれていると考えることができるでしょう。
損失を出さないための対策方法
損失を出さないための対策方法についてですが、売る時期を見極めるというものがあります。どのようなものの売買においてもいえることなのですが、需要が高いタイミングで売却を行った方が売却価格は高くなります。
オリンピックの前などは、不動産の価値が軒並み上昇する傾向にあります。このように、市況を読んで、どのタイミングで売却をするべきかを見極めましょう。
また、不動産の価値が落ちにくくなるように、定期的なメンテナンスも欠かせません。
加えて、なるべく安く購入するというのも大切です。不動産の需要が少ないタイミングで購入し、高いタイミングで売却することを意識しましょう。
マイホーム特例
マイホーム特例とは、居住用物件を売却する場合、いくつかの要件を満たしていれば、 譲渡所得に対し、最大で3000万円の控除が適用される特例です。ここでは、そのマイホーム特例を受けるための手続きや、必要書類の取得方法などを解説します。
マイホーム特例の適用を受けるための手続きは?
マイホーム特例の適用を受ける場合、確定申告が必要となります。申告期間は、居住用物件を売却した翌年の2月16日から3月15日の間、自分の住所地を管轄する税務署で申告をおこなってください。確定申告に必要な書類は、税務署から取得する書類と自分で用意する書類に分かれます。
税務署から取得する書類は
・確定申告書B様式
・分離課税申告書
・譲渡所得の内訳書 です。
最寄りの税務署に足を運び、直接取得しましょう。時間の都合などから、税務署での直接取得が難しい場合、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
自分で用意する書類は、
・売却した物件の購入時と売却時、それぞれの売買契約書(原本、コピー不可)
・売却した物件の登記事項証明書(土地と建物分)
・領収書(仲介手数料や諸費用分など) です。
住民票の住所と売却した物件の所在地が異なるときは、売却から2ヶ月経過して発行された「戸籍の附票」も必要となります。売却した物件がある所在地の役所で取得してください。
不動産売買はタイミングが重要
不動産売買において何よりも重要なのはタイミングです。
そもそも築年数が経過するにつれて住宅の価格は落ちる一方なので、譲渡所得が生まれるケース自体が稀です。
購入したときよりも高く売却をするためには、時期を見定めて販売活動を行う必要があるので注意しましょう。
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。