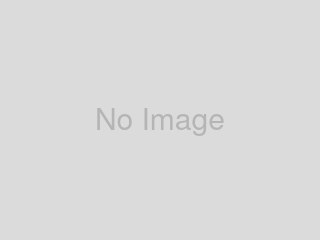建物を取得すると税金が発生しますが、そのとき重要な意味を持つのが減価償却です。
この記事では建物の減価償却について、その内容や計算方法などを詳しく解説していきます。
目次
そもそも減価償却とは?
まずは「建物における減価償却とは何か」について解説していきます。
そもそも減価償却とは
減価償却とは、建物など減価償却資産の取得に際してかかった費用を法律によって定められた年数で分割し、毎年の経費として計上するための計算方法です。なぜ減価償却を行うのか?
減価償却を行う目的は、費用収益対応の原則により、企業の業績や活動の実績を正しく把握することです。費用収益対応の原則とは、損益計算書において一定期間内の費用と収益を一致させるとするルールのことです。
例えば、機械部品1個を1,000円で販売し、月に100個売れたと想定します。部品1個を作成する原価を500円とすると、売上は10万円に対し、費用は5万円となります。
このように収益に対して、それに対応する費用を正しく計上するのが費用収益対応の原則です。これによって収益と費用の関係性が明確になり、事業活動での利益もわかりやすくなります。
減価償却の考え方について
不動産における減価償却は、建物と土地と分けて考えることが重要です。建物は時間の経過によって劣化して価値が落ちていきますが、土地は時間の経過で劣化することはないと考えられるからです。減価償却の計算が必要なケース
建物において減価償却が必要なのは、次の2つの場合に当てはまるときのみです。①不動産の賃貸による収入がある場合
②不動産売却をする場合
たとえばマンションを経営していたり、転勤中にマイホームを貸し出している、マイホームを売却したというような場合に減価償却が必要になります。
建物の減価償却費の計算が必要となるケースは?

建物の減価償却を計算するには定額法と定率法、異なる2つの計算方法についての理解が不可欠になります。
□関連リンク:
「不動産の減価償却とは? 考え方や計算方法の基礎知識」
不動産賃貸による収入がある場合【定額法】
不動産賃貸のような建物の減価償却は、基本的に定額法で計算します。【減価償却費=アパートの取得価額×定額法での償却率】
定額法での償却率は以下の通りです。
| 構造 | 耐用年数 | 償却率 |
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 鉄骨造 (骨格材の厚み3㎜以下) |
19年 | 0.053 |
| 鉄骨造 (骨格材の厚みが3㎜超4㎜以下) |
27年 | 0.038 |
| 重量鉄骨造 | 34年 | 0.030 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.022 |
建築価格で3,000万円、新築で法定耐用年数22年の木造住宅の場合、毎年の減価償却費は次の通りです。
【3,000万円×0.046=138万円】
毎年138万円を減価償却費として計上できます。
不動産売却をする場合【定額法・定率法】
不動産売却においては、2016年(平成28年)4月1日以後に取得した建物か否かで、定率法と定額法に計算方法が分かれます。2016年4月1日より前に取得した不動産を売却した場合、減価償却費の計算方法は以下のようになります。
【減価償却費=未償却残高×定率法の償却率】
定率法における償却率については、国税庁の償却率表を参考にしましょう。
□参考:減価償却資産の償却率等表
次に、定額法での減価償却費の計算については、2007(平成19)年4月1日以降に取得した場合、以下の計算式となります。
【減価償却費=取得価額×定額法の償却率】
2007年4月1日より前に取得した建物の場合、次の方法で計算します。
【減価償却費=取得価額×0.9(90%)×旧定額法の償却率】
一度減価償却の方法を決定すると、残高がなくなるまで同じ方法でしか計算できません。どの計算式で行うのが得になるのか、きちんと計算したうえで決定しましょう。
建物の減価償却の計算方法とは?
続いて償却率に応じた建物の減価償却の計算方法について解説していきます。
定額法
減価償却における定額法とは、毎年の減価償却費が均等になる計算方法です。定額法での計算式は次の通りです。
【減価償却費=取得価額×定額法の償却率】
償却率は法定耐用年数に基づいて決定されるため、国税庁の減価償却資産の償却率等表を参考にしましょう。
定額法で減価償却を行っていく際、耐用年数の最後の年は備忘価格として減価帳簿価額1円を計上するルールがある点に注意が必要です。
定率法
定率法による減価償却は、毎年の減価償却費が一定の割合で減少する計算方法です。毎年減価償却を行う性質上、初年度は最も減価償却費が高く、そこから年々減少していきます。計算式は次の通りです。
【減価償却費=未償却残高×定率法の償却率】
ただし、未償却残高が償却保証額に満たなくなった場合、その年以降は次の計算式となります。
【改定取得価額×改定償却率】
定率法の償却率も、法定耐用年数に基づいて計算されるため、国税庁のサイトから法定耐用年数をチェックしましょう。
建物の減価償却の計算方法に関する注意点
建物は取得時期によって減価償却費の計算方法が異なるため、現在所有する建物をいつ取得したか確認することが非常に大切です。最も大きなものとして、2007年3月31日を境とする旧定額法や旧定率法です。
不動産の取得時期が2007年3月31日以前である場合、事業用不動産の減価償却費の計算は次のように行います。
【減価償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×経過月数/12】
2007年4月1日以降に取得した不動産は、次の計算を行います。
【減価償却費=取得価額×新定額法の償却率×経過月数/12】
非事業用不動産を減価償却する場合は、次の計算式です。
【減価償却=取得価額×0.9×償却率×経過年数・所有年数】
建物における減価償却費の計算シミュレーション
不動産投資を行う際、減価償却費の知識は欠かせません。
建物は時間の経過とともに価値が減少していくため、その分を経費として計上できる仕組みが用意されています。
これは税務上のメリットとなり、節税対策にも活用できます。
ここでは新築マンションを購入したケースをもとに、具体的な減価償却費の計算方法を解説します。
<事例> 新築マンションの減価償却費を計算
今回のケースでは、以下の条件を想定します。
□建物種別:新築マンション
□構造:鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
□取得価格:2億6000万円
□購入年:2018年
建物の減価償却を計算する際は、建物の法定耐用年数が重要になります。
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の法定耐用年数は47年と定められており、一般的に定額法が適用されます。
定額法では、建物の取得価格を耐用年数で均等に割る計算方法を用います。この場合、減価償却の償却率は、
1 ÷ 47 ≒ 0.022(2.2%)
となります。
■ 減価償却費の計算
計算式は以下の通りです。
2億6000万円 × 0.022(償却率)=572万円/年
したがって、この新築マンションでは年間572万円の減価償却費を計上することが可能です。
建物の減価償却費の計算に必要な取得価額(取得費)とは?
建物の取得価格とは、その名の通り建物の取得にかかった費用です。
たとえば、次のようなものが取得価格に含まれます。
・購入代金
・建築代金
・測量費
・建物の取り壊し費用
・登録免許税
・一定の借入利子 など
金額の内訳がわからない場合の取得価額の算出方法
契約書に建物の金額の記載がなく、どうしてもわからない場合は次のような方法で算出することができます。・建物の標準的な建築価額表に記載されている建築価額で計算する
・売買契約書などに消費税の金額の記載があればそこから本体価格を計算する
建物の取得費に含めないことができる費用
建物の取得に発生した費用の中には、減価償却の計算上取得費に含めないことができる項目もあります。具体的には次のようなものが該当します。
・建設計画の変更により不要となった部分の調査
・工事費
・契約の解除による違約金
・建物を取得するために借り入れをした場合、使用開始までに生じる借入金利子など
建物の減価償却費の計算に必要な耐用年数とは?
耐用年数とは、減価償却資産が利用できる年数について法律が定めた年数をいいます。この年数は資産の種類と構造、そして用途ごとに異なっています。
築年数が法定耐用年数を超えた場合の計算方法
築年数が法定耐用年数を超えた建物は次のように計算します。【耐用年数=法定耐用年数×0.2(端数切り捨て)】
築年数が法定耐用年数を超えていない場合の計算方法
築年数が耐用年数を超えていない場合の建物は次のように計算します。【耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×0.2(端数切り捨て)】
償却率に応じた減価償却の計算方法
続いて償却率に応じた建物の減価償却の計算方法について解説していきます。
償却率とは?
償却率とは耐用年数に応じて定められている割合のことです。償却率には定額法と定率法があり、どちらを選択するかによって毎年の減価償却費が異なります。定率法を選択すると、その名の通り定率で計算されてるため初年度の減価償却費が高くなります。
逆に定額法を選択すると毎年同じ額を費用として計上できるようになります。 なお、建物に関しては現在定額法しか選ぶことができません。
償却率の確認方法
償却率は耐用年数をもとに「減価償却資産の償却率表」から算出することができます。詳細は国税庁HPをご確認ください。
□国税庁HP
建物の減価償却費の算出方法・計算例
では、これまで学んだ知識をもとに、実際の建物の減価償却費を計算してみましょう。
新築マンションを購入した場合
上記の条件での計算式は次の通りです。【4億円(取得価額)×0.022(定額法の償却率)=880万円(減価償却費)】
減価償却費累計額と減価償却費との違いについて
減価償却費とよく似た名称を持つものに減価償却費累計額というものもあります。両者の違いについても確認しておきましょう。
減価償却費累計額とは?
減価償却累計額とは、現在までに毎年計上してきた減価償却費の累計額です。減価償却費との違い
減価償却費はあくまで毎年発生する減価償却費の金額です。それが積もり積もったものが減価償却累計額です。1年ごとの部分か、それとも今まで積み上げられてきた部分か、それが減価償却費と減価償却累計額との違いになります。
不動産の売却ならポラスにお任せください
不動産売却の方法や登記申請でお悩みの方は、ポラスにお任せください。ポラスは不動産のプロとして、お客様の大切な不動産の売却を親切、丁寧にサポートします。
不動産売却は大切な住宅を売って終わりでなく、その後の確定申告手続きも含め、煩雑な作業が多くあります。
しかし不動産を売却する機会は、ほとんどの方にとって初めての経験であり、どう進めればよいか迷う方も多いはずです。
「不動産売却で損をしたくない」「確定申告の手続きまでサポートしてほしい」
このようなお悩みのある方は、実績豊富な不動産のプロとともに進めましょう。
ポラスなら不動産売却や登記、確定申告のことまで一括して任せられます。豊富な実績から不動産売却に悩む方へ的確なアドバイスを行い、ワンストップで任せられる不動産の専門会社です。
信頼できる不動産会社をお探しなら、不動産のプロであるポラスにご相談ください。
まとめ
賃貸用に建物を購入すると減価償却費について考えるのが難しいといわれることもありますが、実際にはそれほど難しいものではありません。
落ち着いてポイントを整理し、順を追って考えていくことで驚くほど簡単に建物の減価償却費について理解できることでしょう。
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。