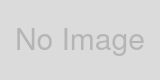家の解体をお考えの方へ
- 一戸建ての解体工事にかかる費用や、更地にするまでの流れがわかります
- 建物を解体するメリット・デメリットを解説
- 自治体の補助金制度もご紹介
また、解体することのメリット・デメリット、自治体からの補助金といった制度も合わせて解説していきます。
目次
家の解体費用の相場
家の解体費用は構造によって大きく変わります。
家の構造による費用相場と坪数による費用の変動について解説します。
家の構造別の費用
家の構造別費用は以下の通りです。・木造:3~5万円/坪
・鉄骨造:5~7万円/坪
・鉄筋コンクリート(RC)造:6~8万円/坪
上記はあくまで目安ですが、木造が最も安く、鉄筋やコンクリートが使用されている家は解体費用が高くなります。これは解体の難しさだけでなく、解体後の処理にも手間がかかるためです。
この他にも立地や付随工事、業者によっても費用は変動するため、相場はあくまでも1つの目安として考えましょう。
【30坪・40坪・50坪】の場合の費用
家の構造と坪数による解体費用の相場についても紹介します。30坪・40坪・50坪の場合をそれぞれみていきましょう。
【木造】の場合
30坪:100~150万円
40坪:120~200万円
50坪:150~250万円
【鉄骨造】の場合
30坪:150~200万円
40坪:200~300万円
50坪:250~350万円
【鉄筋コンクリート(RC)造】の場合
30坪:180~250万円
40坪:250~330万円
50坪:320~400万円
費用はあくまで目安ですので、複数の業者から見積もりを取って比較することが大切です。
家の解体費用が決まる要因
家の解体費用は建物の広さ以外にも、以下の4つの要因によって大きく変わります。
要因① 構造
前述したとおり、土地の広さに加えて、家の構造によっても解体費用は変わります。基本的には、木造、鉄骨造、RC造の順に高くなり、堅固な材料でできている家ほど解体費用がかかります。要因② 施工条件
施工条件が良好かどうかによっても解体費用は変化します。施工条件が良好と判断されるのは、たとえば解体する家の敷地が広かったり、家までの道のりが複雑ではないような場合です。施工条件が良好であれば、解体費用も低くなります。一方、施工条件が悪いとされるのは、敷地や道が狭く重機が使えない、ガードマンをたくさん配置しなければならない、アスベストの飛散防止措置が必要といった場合です。施工条件が悪いと、解体費用が高くなってしまいます。
要因③ 業者の選定
解体業者によって同じ作業内容でも解体費用が大きく異なります。基本的に重機を保有している解体専門の業者に依頼することで、解体費用を抑えることができます。要因④ ごみ処理の有無
解体費用には、ごみの処理費は含まれないのが一般的です。ごみの処理は、ごみの回収業者に別途依頼したり、自治体の粗大ごみで出すなどする必要があります。その際は、有料での対応となり、量が多いほど費用もかかります。解体費用が上がるケースとは

解体する建物や現場の状態・条件によって解体費用は大きく変動します。
ここでは解体費用が上がる3つのケースをご紹介します。
ケース① 地中に撤去すべきものが埋まっている
築年数が古い建物を解体する場合、その地下に古い浄化槽や井戸、地下室等のコンクリートの躯体、不発弾などが見つかることがあります。現場調査をしても見つからず、解体後に発覚するケースも少なくありません。発見後に解体業者が独自の判断で撤去することはないため、売却するためにも合意を交わした上で撤去しなければなりません。撤去の規模が大きくなるほど費用は高くなります。
ケース② 古い建物で有害物質が使われている
1975年以前に建築された建物の場合、有害物質であるアスベストが使用されている可能性があります。除去時に飛散しないように特別な処理を行うため、断熱材にアスベストが使用されている場合は撤去費用が高くなります。使用されている面積によって処理を施す範囲が変わりますが、費用は一般的な解体と比べて2倍程度になることがほとんどです。
ケース③ 天候不順で工期が延びる
家の解体は雨天でも行われますが、安全性が確保できない大雨、積雪や台風といった天候の場合は中止されます。その場合、解体工事は延長されて現場管理や業者の駐車場代などに費用がかかります。結果として追加費用が発生する可能性もあるでしょう。また、工期が延びるということは、売り出すまでの期間も延びることに繋がります。そのため、天候が不安定な時期の解体工事は機会損失に繋がる可能性もあります。
一戸建ての解体の流れ
それでは、一戸建ての解体の流れを見ていきましょう。
①問い合わせ
まず最初に解体業者に問い合わせをします。このとき、1社だけにせず、複数の解体業者に問い合わせして、比較検討することをおすすめします。②事前調査
見積もりをしてもらうために、解体業者に実際に現地を調査してもらいます。事前調査の際にはできるだけ立会い、対応やスタンス、誠実さなどを確認すると、業者を決める際に役立ちます。また、不明な点は質問するとよいでしょう。③見積もり
事前調査に基づき、見積もり書を提出してもらいましょう。確認すべきは、廃棄物処理費用や養生費といった費目と、金額です。「解体工事費」と一括で書かれている場合は、費用に何が含まれているのか、事前に確認したほうがよいでしょう。
また、工事後に費用の上乗せの可能性があるかどうかも聞いておくとトラブルを避けられます。
④契約
見積もり内容に納得したら、その解体業者と契約を結びます。契約の際には、費用の支払い、工期、今後の流れなども教えてくれるはずです。⑤近隣へあいさつ
解体工事では、騒音やちり・ほこりなどが出るため、必ず近隣の方へ挨拶回りをします。その際、作業内容と工事期間を案内するようにすると、トラブルを回避できます。⑥配管・配線の撤去
電力会社やガス会社に停止の連絡をし、その上で、配管・配線の撤去を依頼します。なお、水道は解体工事で使用しますので、通常は停止しません。⑦足場の組み立て
解体工事をする前の準備として、足場を組み、養生シート、防音シートを設置します。こうすることで、高いところの作業ができたり、ちり・ほこりの飛散を防ぐことができ、近隣への迷惑も減らせます。⑧周辺や内部の物を撤去
重機で建物を解体する前に、周辺や内部の物を撤去します。たとえば、瓦や壁材、天井材、畳、建具、住宅設備などです。これらは職人の手によって取り壊し、撤去していきます。⑨建物の解体工事
建物が骨組みだけになったら、いよいよ重機を入れて梁や柱、屋根を解体していきます。このとき、ほこりが飛ばないように、水を撒きながら作業します。⑩廃材の撤去
解体工事で出た廃材を、木材、ガラス、タイル、コンクリート、鉄骨素材などに分別して撤去します。⑪地中物の撤去、整地
建物を取り壊したら、地中に廃材が埋もれていないか、余計なものが埋まってないか確認し、あれば取り除きます。その後、土地を平らに整地すれば解体工事終了です。解体工事にかかる期間の目安
解体工事にかかる期間は、建物の材質や広さによって変動します
期間の目安は次の通りです。
| 木造 | 鉄骨・RC造 | |
| 30坪未満 | 2週間以内 | 3週間以内 |
| 30坪以上 | 2週間以上 | 1ヶ月程度 |
基本的に坪数が増えるほど期間も延びると考え、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。
一戸建ての解体費用の内訳
解体費用には、工事費、廃材処理費以外にも費用がかかることを知っておきましょう。代表的な費用の内訳を解説します。
アスベスト調査、工事
解体工事の前に、建物にアスベストが使用されているかどうかを調査します。これは、法律で義務付けられている調査です。アスベストは、かつては建材に使われていましたが、健康被害を起こす恐れがあるため、現在では使用禁止となっています。
特に1975年以前に建てられた建築物は、アスベストが使われている可能性があります。調査により、アスベストが使用されていると判明すれば、除去する必要があります。
付帯工事費用
付帯工事費用とは、メインとなる建物以外の解体、撤去にかかる費用で、別途必要となります。たとえば、塀や門扉、倉庫、庭木、庭石などです。撤去するものによって、料金は異なります。しっかり見積もりを取り、比較検討することが大切です。諸費用
諸費用に含まれるものは、工事前の近隣へのあいさつにかかる費用や、各種工事に必要な申請の費用、整地費用などです。諸費用も、業者によって料金が異なりますので、見積もりをしっかり取るようにしましょう。解体費用を安くするポイント
家の解体費用は様々な対処をすることで抑えることが可能です。解体費用を安くするポイントを具体的に4つご紹介しますので参考にしてみてください。
ポイント① 相見積もりを取り比較検討する
解体の条件が同じであっても業者によって費用が異なることがあります。余裕があれば2~3社に依頼して相見積もりを取りましょう。見積金額はもちろんですが、工期や工事の質、対応の良さや追加費用など総合的に判断することが大切です。特に信頼性は重要で、工事内容や金額の内訳について根拠を持って分かりやすく説明してくれる業者を探すように意識しましょう。信頼できる業者であれば丁寧な解体を行ってくれて結果的に費用を安く抑えることに繋がります。
ポイント② 不用品処分等をできる限り自分で行う
解体業者は建物内の家具や布団、書籍などの一般ごみや粗大ごみも処理依頼することができます。しかし、解体業者に代行するとそれらの処分は産業廃棄物扱いとなるため費用がかさむ可能性があります。タンスや食器棚などは木くずとして、プラスチックケースは廃プラスチック類として処分できます。数が多くなければまとめて依頼するのも良いかもしれません。また、自力では撤去しにくい大きな庭木は事前に撤去費用を確認しておきましょう。
ポイント③ 固定資産税の課税タイミング
解体は固定資産税の税率変動を踏まえて行いましょう。固定資産税は土地のみと住居用の建物がある場合とで税率が変動します。住居用地の場合は軽減税率制度が適用になっていることがほとんどであり、更地になるとその制度が適用されなくなるためです。
固定資産税は1月1日時点で課税価格が決定します。つまり、その時点で解体終了している場合は、その年から土地の税負担が増えるわけです。売却の時期なども考慮して解体することで、税負担を抑えられるようにしましょう。
ポイント④ 自治体の補助金制度を活用する
空き家が問題視される昨今、解体工事に補助金を出す自治体も増えてきています。事前に市区町村や都道府県のホームページを確認する、または役所に補助金制度の有無について問い合わせてみましょう。地域密着の解体業者の場合は補助金について情報を知っているケースもあります。相見積もりを取るついでに確認してみるのも良いでしょう。また、補助金制度の適用には条件を満たさなければならない場合もあります。条件についても事前に確認し、適用可能かどうか判断することをおすすめします。
ポイント⑤ 空き家解体ローンを活用する
空き家解体には多額の費用がかかるため、預貯金だけで支払うのが難しいケースもあります。 その場合は銀行でフリーローンを組むか、空き家解体ローンを利用するのがよいでしょう。 空き家解体ローンは老朽化した空き家、居住予定のない空き家、解体後の跡地に新築を建てるなどのケースで利用できます。近年の空き家問題を背景に、空き家解体ローンは低金利、無担保で組める商品にしている金融機関も多いです。 保証人も不要にしているケースがあるため、複数の金融機関の商品を比較・検討し、最も利用しやすい空き家解体ローンを選択しましょう。
ポイント⑥ 解体業者の閑散期に工事を依頼する
解体業者にも繁忙期があり、2~5月と10~12月頃は依頼が多く、工期も長くなることで費用も高くなりやすいです。そのため、依頼するなら閑散期の6~9月か1月頃がよいでしょう。 2~5月は引越しが多く、新年度で多くの方が活動的になっていることもあり、多くの仕事があるためです。
また、年内に解体を終わらせたいと希望される方も多く、年末にかけては駆け込み需要が多くなります。
解体費用を安く抑えるには、工期が短縮しやすい閑散期を狙い、短期間に集中して終わらせることがポイントになります。
解体費用の補助金制度一覧
家の解体に補助金制度を設けている自治体もあります。補助金を利用すれば、解体費用を軽減することが可能です。
解体費用の補助金制度とは
解体費用の補助金制度は自治体が行なっている制度です。目的には、街の景観を保つ、放火や犯罪を防ぐ、倒壊などによる近隣への危険性、悪影響を防ぐなどがあります。自治体によって補助金制度を受けられる条件が異なりますので、お住まいの自治体のホームページで確認したり、役所に問い合わせをして、詳細を確認するようにしましょう。
埼玉県さいたま市の建替え工事助成制度
埼玉県さいたま市では、「建替え工事助成制度」があります。制度を受けられるかどうかの条件は、戸建て住宅の耐震診断を実施した結果、「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅です。助成金額は60万円を限度としています。【関連リンク】
「中古の古い家を不動産売却に出す場合は解体して更地にすべき?」
https://www.city.saitama.jp/001/007/002/p022086.html
東京都足立区の解体費用補助金制度
東京都足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。戸建て住宅の解体工事の助成額は、上限50万円です。【関連リンク】
足立区HP(木造住宅・建築物への耐震助成)
https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sokushin-taishin.html
※対象の物件や補助内容などは各市区町村のホームページをご覧ください。
解体費用でローンは組める?
一定の要件を満たせば、家の解体費用のためにローンを組むことも可能です。
住宅ローンは組めない場合もある
解体費用のためのローンが組めるのは、家の解体後に新築工事を行う場合です。この場合、解体費用を含んだ住宅ローンを組むことができます。しかし、家を解体して更地にするだけだと、住宅ローンを組むことはできません。フリーローンや空き家解体ローンの利用
住宅ローンが組めない場合は「フリーローン」や「空き家解体ローン」を利用するとよいでしょう。 フリーローンとは、使い道の制限がないローンです。申請者の事情に合わせてお金を借りることができます空き家解体ローンは空き家を解体するために利用できるローンです。どちらのローンも金融機関で組むことができるので、最寄りの金融機関へ相談してみてください。
家を解体するメリット・デメリット
家を解体することにはメリット、デメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。
解体のメリット
家を解体する主なメリットには、以下3つが挙げられます。・空き家の老朽化による被害を防ぐ
・土地の売却がしやすくなる
・土地を有効活用することができる
解体のデメリット
家を解体するデメリットには、主に次の3つが考えられます。・解体費用がかかる
・固定資産税など税金が高くなる
・区域区分によっては再建築が制限されることがある
家の解体で注意するべき点
家を解体する場合は登記申請や税金のこと、さらには法律についても知っておきたいことがあります。また、トラブルや余計な損失を回避するために、解体する際の注意点をご紹介します。
注意点① 解体後に滅失登記を行う
家の解体後は法務局にて建物滅失登記を行わなければいけません。この登記申請は建物の滅失、つまり解体が完了した日から1か月以内に行うことが義務付けられています。滅失登記を行わないと、解体したはずの建物に固定資産税がかかったり、建て替えができなかったりといった問題が発生します。また期限内に登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性もあるため注意が必要です。
申請手続きは、本人または土地家屋調査士に代行を依頼することが可能です。
注意点② 解体工事をご近所に伝える
解体工事の規模にもよりますが、どんなに配慮しても騒音や振動が起こるものです。近隣トラブルを回避するためにも、事前にご近所には解体工事をする旨を周知しましょう。また、解体後に建て替えも予定している場合は工期が長くなります。建て替え後に売却し、買主様が住みにくくなるようなことがないように、しっかりと周知しておきましょう。注意点③ 更地のままだと固定資産税が高くなる
居住用の建物が建っている土地は住宅用地の特例が適用となっています。土地の評価額が200平米まで6分の1となるため、固定資産税もかなり減税されています。しかし、解体して更地にすると特例が適用されないため固定資産税・都市計画税がそれまでと比べて増えます。毎年1月1日時点の状態によって課税額が決定されるため、それを踏まえて解体・建て替え・売却を検討しましょう。
注意点④ 再建築の可不可を確認しておく
家が古い場合、解体後に建築基準法によって再建築不可となるケースがあります。これは建築基準法が改正されたためです。再建築不可の土地は売却する際に大幅に値引きされる可能性が高いです。もし再建築が不可である場合は、解体せずに古家つき物件として売る方が良い場合もありますので、検討してみましょう。
いずれにせよ、解体前には必ず再建築可能かどうかを確認してください。
家の解体費用は補助金やローンで負担を軽減できる
家の解体費用は、広く、堅固な材料で作られているほど高額になります。ただし、各自治体が行なっている補助金制度や、金融機関のローン制度を利用することで費用の負担を軽減できます。
家の解体をお考えの方は、それらの制度を活用するとよいでしょう。
【関連リンク】
「中古の古い家を不動産売却に出す場合は解体して更地にすべき?」
https://www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=123
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。